今の健康保険料の負担額がいくらか、答えられますか?
早期リタイアした場合、社会保険料がいくらになるか把握していますか?
会社員の皆さんが毎月支払っている健康保険料。税金は気にする人も多いですが、この健康保険料にはあまり関心の無い人が多いかと思います。
健康保険料は給与から天引きされているので、上げられても気づいていない人が多いと思います。
今回は、これまでの健康保険料の推移やこれからどうなるのか。
そして、早期リタイアした後、健康保険料はいくら掛かるのか。
この2点について解説していきます。
目次
健康保険とは
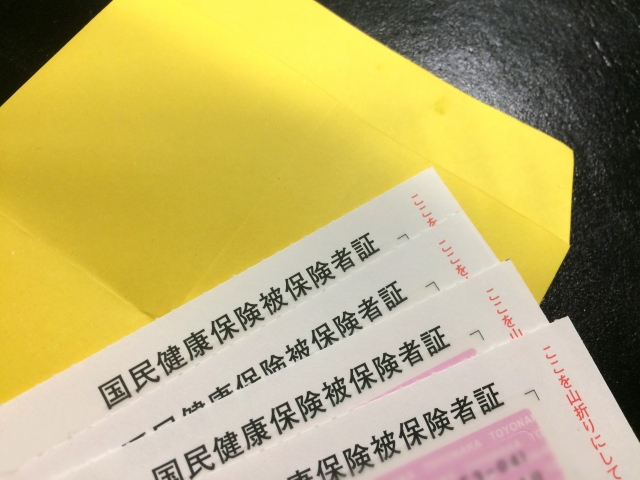
健康保険は正しくは公的医療保険と言い、病気や怪我で病院にかかる時や、傷病によって仕事が出来なくなった時など、大変な事が起きた場合に大きな経済負担が掛からないように、ある程度金銭的に助けてくれる制度です。
みんなで保険料を出し合って、困っている大変な人を助け合いましょう、という制度ですね。
公的医療保険は、「健康保険」「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」の3つに分かれます。
健康保険・・・会社員とその家族が入っている保険。サラリーマンが入っている保険ですね。
国民健康保険・・・上記の健康保険に入っていない人。つまり、自営業者や未就業者が入っている保険。早期リタイアすると、この保険に加入にする事になります。
後期高齢者医療制度・・・主に75歳以上の人が加入する制度。今回はあまり関係ないので割愛します。
会社員の健康保険料はどう決まっているか。計算式
社会保険の場合、「標準報酬月額×保険料率」で計算出来ます。(標準報酬月額は、給与が多いほど高い。)
そして、このうち半分を会社が支払ってくれるため、上記を2で割ります。
例えば僕の場合、ザックリですが
標準報酬月額が470,000円、保険料率が10%だと、
470,000円 × 10% ÷2= 23,500円 が、その月の健康保険料になります。
これまでの保険料率の推移
この健康保険料を決める重要な要素である保険料率。
これまでどのように変化してきたのか見てみます。
健康保険は、「協会けんぽ」(主に中小企業)と、「組合健保」(主に大企業)の2つに分かれますが、ここでは協会けんぽの保険料について解説します。
| 年度 | S22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 42 | 51 | 52 | H2 | 21 | 23 | 24 |
| 料率(%) | 3.6 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.2 | 9.5 | 10.0 |
平成21からは医療費の地域差を減らす目的で都道府県ごとに保険料率が違うため、平均保険料率になっています。都道府県ごとに大きな差はなく、令和2年度の保険料率の最低が新潟県の9.58%、最高が佐賀県の10.73%です。
少しずつ上がって、昭和22年から比べると3倍近くになっています。
これからどうなるのか?
社会全体の医療費が増えるほど、また社会全体の稼ぎが減るほど資金が枯渇するので、健康保険料の率を上げる必要が出てきます。
また、現役世代の保険料のうち一部は、75歳以上の後期高齢者支援金分として負担をしています。
高齢化社会が進んでいる日本では、保険料率を上げざるを得ないですよね。
今後、確実にこうなる、と明記された記事は見当たりませんが、健康保険組合連合会によると、2022年に団塊の世代が75歳以上になる年として「22年危機」と呼び、警鐘を鳴らしています。
今の健康保険料では現行の制度の維持は出来なくなる可能性は高いのは間違いありません。
早期リタイアした場合の保険料
早期リタイアにより、会社を完全に辞めた場合、社会保険(社保)を脱退して国民健康保険(国保)になるので、そもそもの保険料の計算方法が変わります。
国民健康保険の場合、市区町村によって異なりますが、基本的に前年の所得等、以下の4つに分けて計算されます。
所得割:所得により決まる保険料。つまり、高い所得ほど保険料が上がる
資産割:持っている固定資産(土地や建物)の価格により保険料が決まる。
均等割:1人増えるごとに定額で増える保険料。
平等割:世帯ごとにかかる保険料。
所得割について、早期リタイアする場合の収入源である株の売却益や配当金ですが、運用する口座を特定口座の「源泉徴収あり」にしておく、つまり確定申告をしなければ、これら所得は国民健康保険料の対象にならず、社会保険料が安くなります。(資産割や均等割りがあるため、ゼロ円にはなりません)
例として、とある市区町村のシミュレーターを使って、仮に「妻と子1人で、リタイア後の収入は株の売却益と配当金のみ、確定申告をしなかった場合(その他の所得は無い場合)」で計算してみたところ健康保険料は下記のとおりでした。
年間47,880円、一月あたり3,990円
思ったより安いです。現在の自分の健康保険料(約23,500円)と比べると格安ですね^^
ちなみに世帯の前年所得が33万円以下だと、保険料が7割の減額を受けられます。上記シミュレーションは、所得ゼロ状態ですので、7割の減額を受けた結果です。
ただし、確定申告をする事で税金の還付を受けられる場合もあるので、確定申告をしない方が良いかどうかは一概には言えず、税金と保険料を総合的に判断する必要があります。
また、国民健康保険は市区町村により金額等も大きく異なるため、詳細は住んでる市区町村の自治体に問い合わせるのが確実かと思います。
例として、藤沢市のHPを載せておきますのでご覧ください。
外部リンク >>>株式や配当などの確定申告と国民健康保険料
健康保険(サラリーマン)と国民健康保険(早期リタイア後)の比較
一般的に、健康保険の方がお得、と言われています。
健康保険のメリットとして
①健康保険は扶養している家族の給与は保険料に上乗せされない
②健康保険は保険料の半分は会社が負担してくれるが、国民健康保険では自分で全額支払う。
③国民健康保険の場合、傷病手当や出産手当(傷病や出産で働けなくなった期間の保障)が無い
などがありますが、
②については、会社が半分負担するとは言え、その負担してもらっている分、給与に影響している(下げられている)可能性は否定できないので、本当に会社負担が良いのか、という疑問はあります。
③については、そもそも「傷病や出産で働けない」場合って、リタイアしていれば困る事はないですね。
まとめ
早期リタイアした場合、確定申告をするかどうかで大きく保険料が変わるため、ケースバイケースになってしまうので、税金と保険料を総合的に判断する必要があります。
自分の場合、どの選択をするのがベターなのか、勉強しながら早期リタイアに備えたいと思います。



コメント